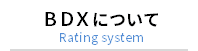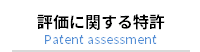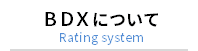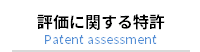|
|
|
|
① |
定期的に実施されている勤務評価結果の副産物として、評価対象者のリスク情報を見える化できるため、企業においてはリスク管理のための新しい工数(リスク調査など)は不要であり、既存の勤務評価を実施する都度、継続して評価対象者のリスク管理を行うことができます。 |
|
|
|
|
② |
評価対象者は、これまで知ることのできなかった、自身の仕事に潜むリスクを事前に知ることができるため、これまでのような「リスクの発生は運まかせ、失敗は経験して学べ」という、危険がつきまとう業務を行うのではなく、さまざまなリスクや失敗事例を充分に理解したうえで業務を行うことができます。(失敗の少ない組織づくりが可能になります。) |
|
|
|
|
③ |
評価対象者の苦手な評価項目(評価値が低い項目)からリスクを見える化することができるため、評価対象者にあらわれやすいリスクの芽を未然に摘み取ることができます。また評価対象者は、評価項目が達成できなかった場合の該評価項目に関するリスクや失敗事例などを知ることができるため、勤務評価における「評価項目の重要性や本質、意義」を理解することができます。 |
|
|
|
|
④ |
従業員の教育面において、これまでの社員研修に加え、従業員一人ひとりに潜むリスクへの研修(これまで見えなかった部分の研修)もできるようになります。 |
|
|
|
|
⑤ |
評価対象者は自身の苦手分野に潜むマイナス面(リスクや失敗事例)を事前に知ること、または改善することができるため、オンボーディングやエンゲージメントの向上に繋げることができます。 |
|
|
|